【はじめに】お店に行く(ネット注文する)その前に、5分だけ確認してください
「四十九日までに、本位牌を作らなきゃ…」
そう思って、いきなり仏具店に行ったり、ネットショップで注文しようとしていませんか?
ちょっと待ってください。
手ぶらでお店に行く(またはネットでいきなり注文する)と、「戒名の漢字が分からない」「サイズが合わない」といった理由で、二度手間になってしまうことが非常によくあります。
通常、位牌の作成には2週間ほどかかります。もし注文内容に不備があってやり直しになると、四十九日法要に間に合わないという事態にもなりかねません。
だからこそ、事前の準備が不可欠なのです。
 スギ
スギこんにちは。「仏具の教科書」のスギです。
この記事では、あなたが注文前に準備すべき「持ち物」と「確認事項」を、チェックリスト形式でまとめました。
この記事をスマホで見ながら準備するだけで、相談や入力作業が驚くほどスムーズに進み、絶対に失敗しない位牌作りができます。
1.【出発前】これだけは揃えよう!必須の持ち物リスト
お店に行く、またはネットで注文画面を開く前に、以下の情報を必ず揃えてください。これがないと、正確な注文ができません。
- [ ] 白木位牌(仮位牌)の写真
→ 【最重要】 表と裏、文字がはっきり読めるようにスマホで撮影してください。これが、戒名などの文字情報の全てです。 - [ ] 四十九日法要の日付
→ 納期を確認するために必須です。 - [ ] お仏壇の「位牌を置くスペース」の寸法
→ 高さ・横幅・奥行きを測ってください。特に「高さ」は重要です。お仏壇の上から二段目の左右どちらかに置くようになります。 - [ ] (ある場合)ご先祖様の位牌の大きさ、デザイン
→ ご先祖様の位牌と横並べにする際に、高さを揃えたい場合は確認しておくとよいです。ただし、必ずしも同じ大きさ、デザインにする決まりはありません。生活環境の変化により、位牌を祀る場所などが変わった時は、今の環境に合わせたものを選びましょう。
【プロの補足:未来を心配しすぎないで】
「将来引っ越すかもしれないから」「子供に負担をかけたくないから」と、先のことを心配しすぎて、あえて小さすぎる位牌を選んだり、位牌作り自体を躊躇してしまう方がいらっしゃいます。しかし、先のことは誰にも分かりません。大切なのは、「今、この瞬間」を生きている私たちが、故人を想う気持ちを、最高の形で表現することです。
今の生活環境の中で、無理のない範囲で、しかし心を込めて「良いもの」を選ぶ。それが、故人への何よりの供養になります。せっかくの「手を合わせたい」という尊い気持ちを、未来への不安で粗末にしないでください。
2.【店内・ネット注文】スムーズに決めるための「伝え方」ガイド
お店のスタッフに相談する際や、ネットで商品を探す際は、以下の順序で進めるとスムーズです。
① 「四十九日の本位牌を作りたい」と明確にする
まずは目的です。法要の日付(納期)に間に合うかどうかが最優先事項ですので、最初に確認しましょう。
② 予算とイメージを伝える(探す)
「予算は〇万円くらいで」「黒い伝統的なものがいい」「家具調のモダンなものがいい」など、ざっくりとした希望を伝えます。
具体的な金額や位牌の種類を知りたい方は、下記の記事を参考にどうぞ。
▼イメージを固めたい方はこちら
[⇒リビングに合うおしゃれな「モダン位牌」10選を見る]
[⇒種類を詳しく知りたい方は『本位牌の完全ガイド』へ]
▼【職人推薦】ネットで買える「最高品質の国産位牌」を知りたい方はこちら
[⇒【職人が語る】江戸草葉の位牌レビュー(国産・本物)]
③ 白木位牌の写真を見せる(アップロードする)
ここで、撮ってきた写真が活躍します。
お店なら店員さんに、ネットなら注文フォームやメールで写真を送ることで、宗派や文字数、梵字の有無などをプロが確認してくれます。
もし、既存の位牌に合わせて作りたい場合は、その位牌の表と裏の写真、または文字を書き写したメモを持参しましょう。「文字の色(金か白か)」や「梵字の有無」も重要な確認ポイントです。
3.【注文時】後悔しないための「最終確認」ポイント
デザインが決まり、いざ注文する時。ここが失敗しないための最後の砦です。
- [ ] 文字のレイアウト(配置)は確認しましたか?
→ 夫婦連名にする場合などは、左右の配置に注意が必要です。
[⇒【職人が解説】文字入れで失敗しないための全注意点はこちら] - [ ] 「校正(こうせい)」の方法を確認しましたか?
→ 彫刻する前に、文字の確認図(校正紙)を見せてもらえるか、必ず確認してください。ネット注文の場合も、メールやFAXで確認できるお店を選びましょう。 - [ ] 総額はいくらですか?
→ 「文字彫り代」が含まれているか、必ず確認しましょう。基本的には、「位牌本体価格 + 文字代 = 総額」です。
4.本位牌【受け取り後】の四十九日法要までの流れ

完成した位牌を受け取ったら(届いたら)、以下の手順で当日を迎えます。
- 文字の間違いがないか、再度確認する
→文字の間違いや疑問がある場合は、購入店にすぐに連絡しましょう。 - 四十九日法要まで、箱に入れたまま大切に保管する
→ 四十九日までは白木位牌がメインとなるため、本位牌はしまっておきます。 - 法要当日、白木位牌と本位牌を準備する
→ お寺様による「開眼供養」を経て、本位牌が正式なものとなります。お寺やその他の場所の場合は、必要なものをお寺様に事前に確認しておきましょう。 - 白木位牌をお寺様に引き上げてもらう
→ 白木位牌は四十九日までの仮位牌です。必ずお寺様に引き上げてもらいましょう。
【まとめ】準備さえすれば、位牌作りは難しくない
位牌作りで最も大切なのは、「正確な情報を伝えること」です。
このチェックリストを使って準備をすれば、実店舗でもネット注文でも、プロがあなたをしっかりとサポートしてくれます。
位牌は文字入れをしてしまうと、修正や変更が難しいです。長く手を合わせていく仏具なので、後悔のないように作ることが大切です。
安心して、故人への想いを込めた、素敵な位牌を作ってくださいね。
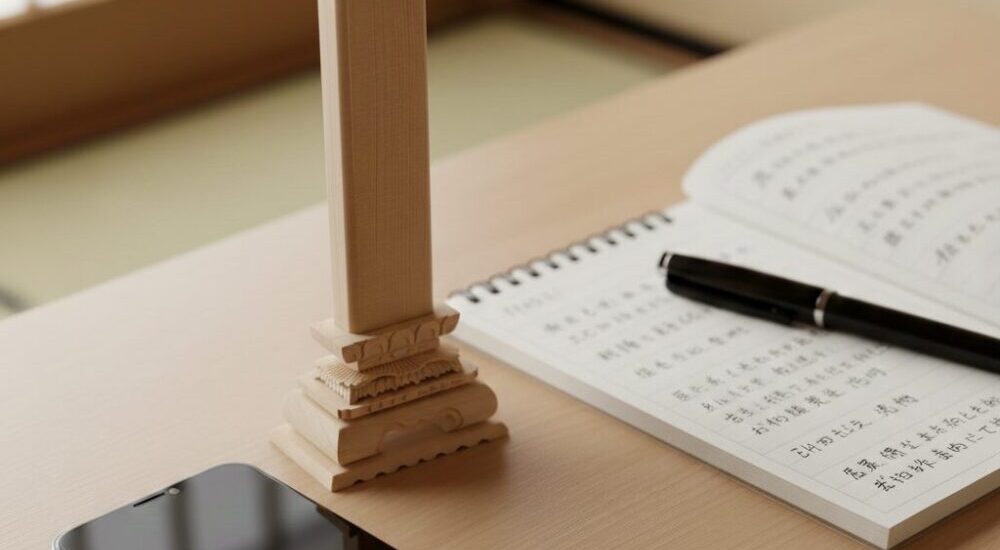









コメント